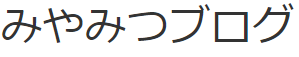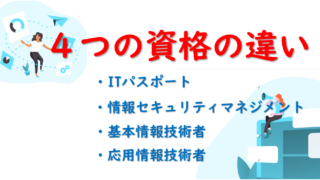このブログは資格勉強をテーマにお役立ち情報を紹介しています。
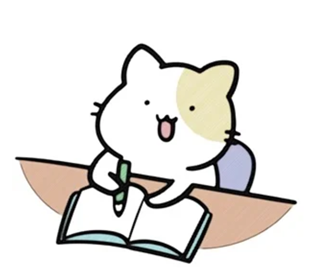
基本情報技術者試験について知りたい。おすすめの勉強法は?
このような、基本情報技術者試験に関する質問にお答えします。
- この記事で分かること
-
- 基本情報技術者試験とは?
- 勉強ツール13選
- 効率の良い勉強法
- 初心者の勉強法
- 試験申込や当日までの準備など
この記事では、「これから基本情報技術者試験の受験を考えている人」に向けて必要となる情報をまとめました。
少しでも資格勉強の手助けになればと思います。
基本情報技術者試験について

基本情報技術者試験は「ITエンジニア向けの国家資格」です。受験者数も毎年10万人程度と人気の資格です。キャリアアップや受験/転職にも有利になります。
以下の記事では、基本情報技術者試験のメリットや試験概要、さらに、ITパスポートや応用技術者試験との違いを理解できます。
基本情報技術者試験とは?
ITパスポートや情報セキュリティマネジメントや応用技術者試験との違いは?
勉強ツールについて

基本情報技術者試験の勉強ツールは、無料・有料のものを含めて13種類あります。自分に合ったものを見つける手助けになればと思います。
以下の記事では、基本情報技術者試験の勉強ツールについて紹介いたします。特に参考書とUdemyと過去問の3つがおすすめです。
①すべての勉強ツール【13選】
②参考書
最新シラバス対策を確実に行うことができます。
③Udemy動画
コスパNo1の勉強ツールです。効率良く勉強できます。
④スタディングアプリ(動画)
スマホで全て勉強できます。進捗管理機能もあり人気です。
⑤過去問の活用法
効率の良い勉強法

基本情報技術者試験は、試験範囲がかなり広いので、勉強に200時間が必要と言われています。このため、効率よく勉強することが大事になります。
以下の記事では、基本情報技術者試験の効率の良い勉強方法について理解することができます。
合格に向けた最短勉強法
勉強時間が50時間以下を目標に、効率の良い勉強法を紹介しています。
過去問は何年分解くのがよいか
初心者の勉強法

基本情報技術者試験は「ITエンジニア向けの試験問題」なので、初心者のひとにはかなり難しいです。特に科目Bのアルゴリズムとプログラミングは、配点が8割もあり、勉強には注意が必要です。
以下の記事では、基本情報技術者試験の難しさと、初心者のひとが独学で勉強する方法について紹介しています。アルゴリズムとプログラミングについても取り上げました。
①試験の難しさについて
②初心者が独学で合格する方法
③アルゴリズムの勉強法
④プログラミングの勉強法
試験申し込みや当日流れ
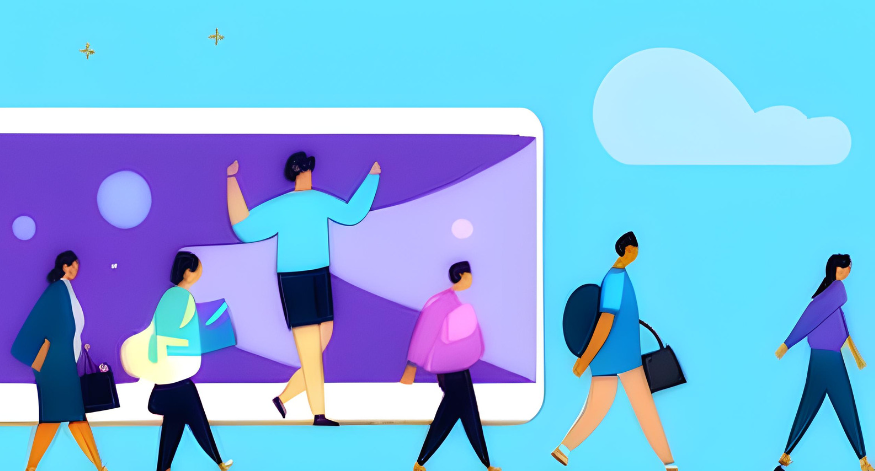
基本情報技術者試験の試験申込から、当日までの準備、当日の持ち物、合格発表までを、まとめています。
以下の記事では、最新の試験申込から合格発表までを理解することができます。2023年4月からは、試験主催者がプロメトリクスからIPA(情報処理推進機構)に変更になったので、最新情報について知ることができます。
試験申込、当日までの準備、持ち物、合格発表
合格後はITエンジニアとして活躍

基本情報技術者試験に合格したら、基礎的なIT知識を所有している証明となります。
IT初心者や未経験者の方はプログラミングについても勉強していきましょう。
特に、就職支援、フリーランス支援(副業)が確約されるプログラミングスクール「TechAcademy」で学習するのがおすすめです。
なぜ、独学でなく、プログラミングスクールがおすすめなのかについても下記の記事にまとめていますのでご覧ください。
》プログラミングを最短でマスターして稼ぐ方法
少しでも資格勉強の助けになれば幸いです。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。